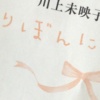2008~2010年にアシックスがWEB上のキャンペーン「マラソン三都物語~42.195km先の私に会いに行く~」のために三人の作者によって書き下ろされた、3編からなる短編集。
以下、心にとまった点、気になった点を。
一つ目は、三浦しをんによる「純白のライン」。
舞台はニューヨーク・シティマラソン。
スタートがスタテン島だというのは知らなかった。
てっきり、スタテン島は陸地ではつながっていないものと思っていたので。
スタートと同時に参加者が脱ぎ捨てる防寒用のシャツやジャンパーなどは、ボランティアが拾い集めて寄付にまわすそうだ
これも知らなかった。面白い試み。
高架下などのトンネル状の薄暗い場所で、オランダ人は必ずと言っていいほど声を上げる。彼らの習性なんだろうか。
これはどうなんだろう。ネットでちょっと調べた範囲ではそういった記述は見当たらなかった。
2つ目は、あさのあつこの「フィニッシュ・ゲートから」。
舞台は東京マラソン。
主人公はシューズメーカーで働く。その上司であるシューズの名工に「おまえはいつまで経っても中途半端」だと呟かれ、かっとする主人公。それに対し、
言うてみ、なんでかっとした?
図星やったからやろ。人間、痛いところを突かれると頭に血が上るもんや
と。
正直主人公の「中途半端」感は伝わってこなかったが、名工の言うことはわかる。
主人公の同級生冠城について、高校時代にその姿を陸上競技場で目にした名工は、一流アスリートに遜色ない眼をしていたと言う。
こいつはただ走りたいから走るんやなって、こっちを納得させてくれるみたいな眼をしてたんや。成績とか順とか……例えばメダルを首にかけてもらうとか、最初にゴールインするとか、勝者として称えられるとか、うん、そういうのをあっさり超えちまって、ただ走ることだけを見ている眼
東京マラソンのコースについて。
あそこは、本気で走るつもりならなかなか手強いで。コース設定が絶妙やからな。フラットに見えて細かなアップダウンがけっこうあるし、単純な風景が続く。沿道は人で溢れ、声援が惜しみなく送られる。つい、走りすぎてしまうんや。それで、オーバーペースの疲れがな、ボディブローみたいにじわじわ効いて、残り七キロあたりで、どうにも脚が動かなくなる
確かに、経験が浅いランナーだと「走りすぎてしまう」面もあるだろう。
3つ目はパリマラソンが舞台の、近藤史恵の「金色の風」。
慣れないパリの生活に振り回される主人公の女性。
なにより、こちらの人は感情を隠さない。日本では面倒な客だと思っても、笑顔で対応してくれるが、こちらではことばがうまく喋れないと、呆れたように肩をすくめられる。そのたびに心がずきりと痛んだ。
流暢に喋れるのならば、そもそも留学なんかしていない。喋れるようになるためにきているのだ。そう思って自分を鼓舞するけど、やはりなにかあるたびに気持ちは落ち込んだ。
わたしは気づいている。それはこの街が悪いわけではなく、たぶんわたし自身が悪いのだ。
整理できないものがたくさん、わたしの中で蠢いている。
部屋に帰ってから、朝美にメールを打った。
わたしの感情は、どの文字にも引っかからず、空しく滑り落ちて消えた。
言葉が不自由な状態で、ひとりっきりで異国の地に身をおく厳しさは、体験したものにしかわからないだろう。
「感情がどの文字にも引っかからない」。
文学的だが、共感できる感覚。
主人公が現地で知り合ったチェコ人の女性と、バレエと歌舞伎の違いについて話す。
どちらも子どものときから訓練するが、能や歌舞伎は世襲制で、バレエにおける自分のような脱落者はあまり出さないと。
チェコ人女性は言う。
たぶん芸術というもの自体が、犠牲を必要としているのよ。
バレエというものが、あなたみたいな人を必要としているの。あなたのように振り分けられた人がいるから、一握りの才能が見つけ出せた。あなたのことばを借りれば、砂を拾い集めなければ砂金は見つからないの。カブキのシステムは違うけど、そのシステムではカブキは作れても、バレエは作れないわ。
だから、あなたもバレエという芸術の一部なのよ
残酷な世界だが、それが現実だろう。
パリマラソンを走りながら。
ふいに思った。たぶん、走ることは祈りに似ている。
身体の隅々まで酸素を行き渡らせて、身体を透明にして、祈る。
そろそろ息が荒くなってくる。いちばん苦しくなる時期だ。踊っているときにも、こんなときがあった。
泣きたいほど苦しくて、やめたくて、どうしてこんなことをやっているんだろうと思って。
そう、なにもかもが同じで、繰り返しだ。わたしたちは同じことを繰り返す。
でもわたしは知っている。ここを越えれば、また幸福を感じる時間がやってくる。
思い出した。踊っているときもそうだった。
ありきたりな表現だなとも思う。
が、それでも走ること、生きることを考えさせれられる一節。
短編集ということもあり、全体を通して強い印象はない。
が、ランナーだったら読んでおいてもいいんじゃないだろうか、という程度の心へのひっかかりは提供してくれる作品である。